こんにちは ねこの静六です。
今回はガーデニングや野菜栽培をしているとかなりの頻度で出会うヨトウムシについて特徴や対策、使った薬剤について書きたいと思います。
私が初めてヨトウムシに出会ったのは園芸を始めたばかりの頃にハーブのタイムが1日でほとんど枝だけになってしまった時でした。かなりびっくりしました。
ヨトウムシとは?


ヨトウムシの対策方法
露地栽培で農薬を使用せずに対策する事は結構大変です。
ヨトウムシに効果のある薬剤
ヨトウムシに効果があり、私の使用経験がある薬剤を紹介します。
ベニカベジフル乳剤
ヨトウムシ、アオムシ、アブラムシ、コナジラミなど色々な害虫にとても効果があります。
2020年11月現在でかぶとにがうり(ゴーヤ)に適応が無いことが残念ですが、これほど適用害虫と適用作物が多い噴霧農薬が無いので家庭菜園ではかなり重宝しています。薬液も希釈だけなので簡単です。効果もすぐに現れます。成分のペルメトリンは虫除け効果もあります。
同じペルメトリンが成分のアディオン乳剤(ペルメトリン20%)にはかぶとにがうり(ゴーヤ)にも適用があるのでより広く使えます。ペルメトリンの濃度がベニカベジフル乳剤よりも濃いのでより希釈する必要があります
トレボン乳剤
トレボン乳剤の使用感はアオムシやヨトウムシ、アゲハの幼虫などへの効果は先ほどのペルメトリン農薬より即効性と効果がありました。効果が良くてクモなどの益虫への影響が少ないので使いやすいです。こちらも希釈するだけなので簡単です。
2020年11月現在でキクナ、ほうれん草、小松菜、かぶなどの適用がまだ無いことがデメリットかもしれません。先ほどのペルメトリン農薬よりも葉物に適用が少ないのが私の印象です。
ゼンターリ顆粒水和剤
BT菌とは、昆虫病原性細菌/バチルス チューリンゲンシス(BT)という微生物の総称です。BT菌は芽胞形成時、菌体内に結晶性の殺虫タンパク質を作り、食毒性を持っています。対象害虫が摂食で生芽胞及び結晶性殺虫タンパク質を体内に取り込むと、消化管内のアルカリ条件とタンパク質分解酵素の働きで、毒素が活性化します。取り込まれた殺虫タンパク質は、やがて消化管の特定部位に結合し、細胞を破壊します。細胞破壊により体液が消化管内に流入することで腹下りを起こし、摂食を止めて、最終的には生芽胞から発芽したBT菌が体内で増殖し、死亡してしまいます。
日本生物防除協議会HPより引用
BT菌は自然界に広く生息しており、世界各地から数多くの系統が分離されています。中でもクルスターキ(kurstaki)、アイザワイ(aizawai)系統を菌株とする製品が農薬登録されており、一般的にBT剤として防除に利用されています。
ゼンターリ顆粒水和剤はヨトウムシに対して初めて購入した農薬です。その時は有機栽培でも使用できるという一点で購入しました。ゼンターリ顆粒水和剤はヨトウムシなどの幼虫にはとても即効的です。ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、メイガ、オオタバコガといった幼虫系にのみ効果があるのでターゲットは狭いのでゼンターリだけで多くの害虫に対応する事は出来ませんが、安全性は高い薬です。使用の際には植物に薬剤がきちんと付着するように展着剤(ダイン等)を使用する方が良いです。
植物の葉っぱにはワックス成分のようなものがついているため、単純に水分を吹きかけてもはじいてしまいます。そのため水和剤などの農薬に界面活性剤の入った展着剤を混ぜて使います。
ヨトウムシの特徴・対処法・適用薬剤について書いてみました。
自身の作物を育てる上でのポリシーを意識しながら最適な選択が出来るヒントになれば幸いです。今日もありがとうございました。
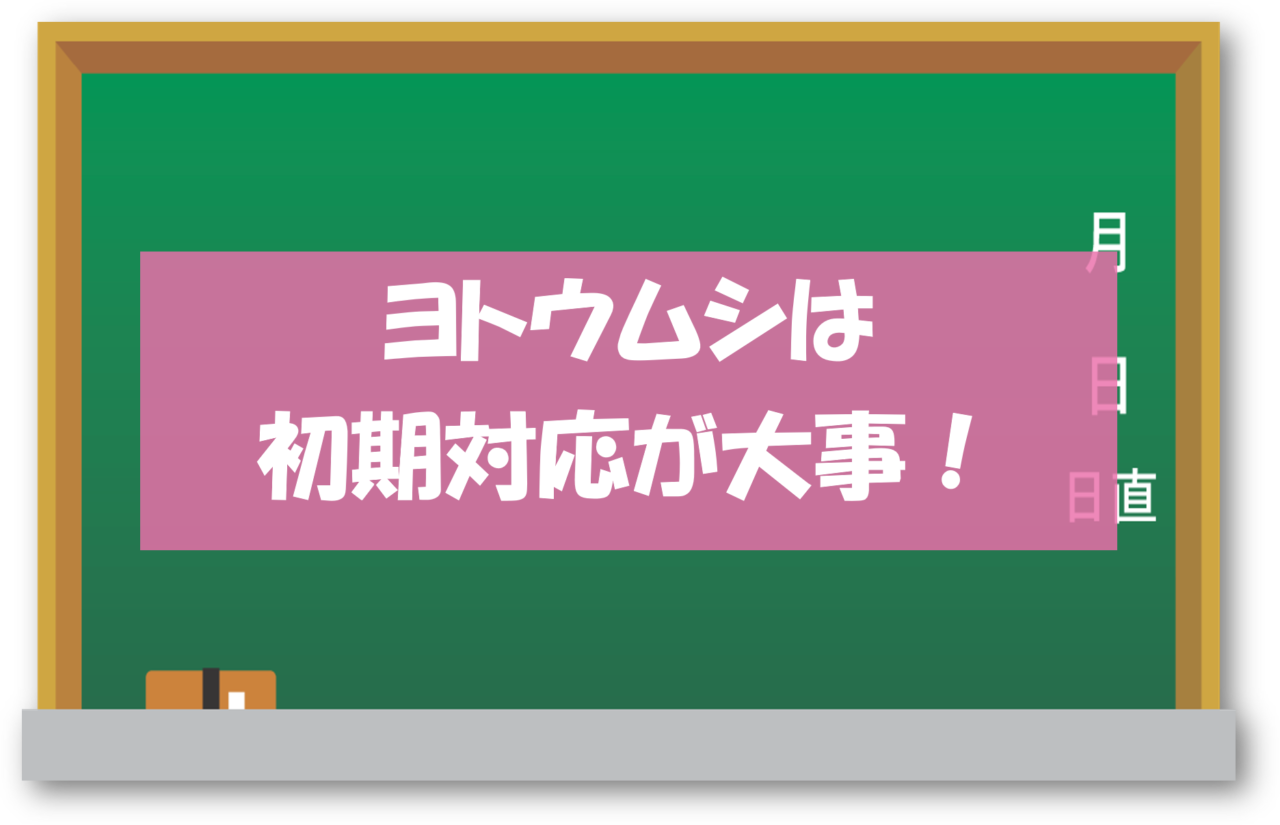
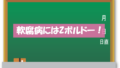
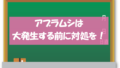
コメント